 数学の欠片
数学の欠片 努力の工夫
どんな本や理論を学ぶにしても、体力や知力が必要で、その体力や知力をつけるための工夫や努力は、どの分野の達人を見ていても「凄い」と感じる事がある。 どう、その山(本や理論)を攻略するか、という事はまちまちのようにも感じるのだけれど、ある山を攻...
 数学の欠片
数学の欠片  数学の欠片
数学の欠片  数学の欠片
数学の欠片 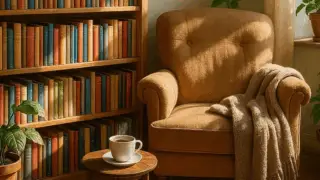 数学の欠片
数学の欠片  数学の欠片
数学の欠片  数学の欠片
数学の欠片  数学の欠片
数学の欠片  数学の欠片
数学の欠片  数学の欠片
数学の欠片  数学の欠片
数学の欠片