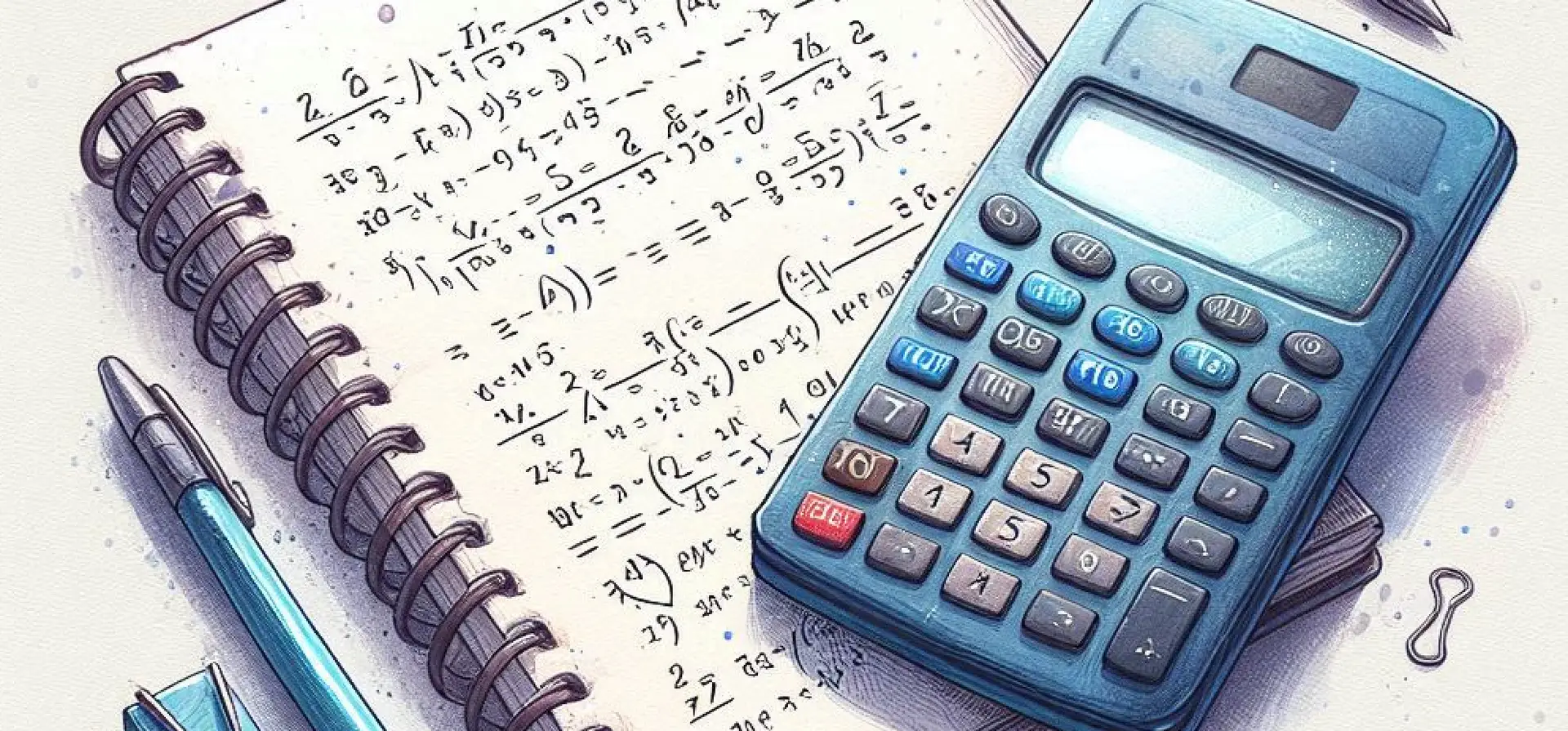一つ、証明をしてみよう。
例えば、私の愛読している数学書には、ある定理に関してこう書かれている。
|
$c$. 一般に次の定理が成立する(特に$a$ が $b$ で割り切れる場合も含めて): どんな整数$a$ も、正の整数$b$ によって、一意的な仕方で次の形に表される: $a=bq+r$ ; $0\leqq r<b$ 実際、$a$ のこのような形への表示の一つは、$bq$ を数$b$ の倍数であって$a$ をこえない最大のものに等しく取ることによって得られる. $a=bq_1+r_1$, $0\leqq r_1 <b$ という形にも表すことができるものとすれば、 $0=b(q-q_1)+r-r_1$ が得られる. これから従うように, $r-r_1$ は$b$ の倍数である ($b$, $2$). ところが, このことは, $r-r_1=0$ である場合, すなわち $r=r_1$ である場合にのみ起こり得る. これから $q=q_1$ も出てくる. 略 (引用元 『復刊 整数論入門』 H.M.ヴィノグラードフ 著 三瓶与右衛門・山中 健 訳) |
今日は、この文章をどう読み込む事で、
厳密な証明を得られるか、それを行ってみよう。
まず、この定理を証明するためには、
証明に際して必要な「仮定」を探し出す必要がある。
証明の「仮定」とは、数学書のどこかには書かれていると思う。
ただ、その「仮定」が、ある証明の道筋に
どう書かれているかは、数学書ごとに異なる。
従って、数学書のどこに「仮定」が書かれているか、
それを探す事は、数学書を読み込むための必要条件である。
この時、この文章内で「仮定」として参照すべきは、
「実際、$a$ のこのような形への表示の一つは、
$bq$ を数$b$ の倍数であって$a$ をこえない最大のものに
等しく取ることによって得られる」
という箇所である。
また、結論として与えられている箇所は、
「どんな整数$a$ も、整の整数$b$ によって、
一意的な仕方で次の形に表される: $a=bq+r$ ; $0\leqq r<b$」
という部分である。
従って、「$p$ である時$q$ である」
つまり「$p \Rightarrow q$」という形を作りたければ、
「$bq$ を数$b$ の倍数であって$a$ をこえない最大のものに
等しく取る
$\Rightarrow$ どんな整数$a$ も、正の整数$b$ によって、
一意的な仕方で次の形に表される : $a=bq+r$ ; $0 \leqq r< b$ 」
とおく必要がある。
証明とは、仮定と結論の間を埋める作業であるから、
この間が埋められさえすれば、証明が成立する。
ちなみに一意的というのは、「たった一つの」という意味で、
「$a=bq+r$ ; $0 \leqq r<b$ という形が唯一である」という意味である。
この時、気にしなければいけない事として、
この結論には2つの含意があるという事で、
一つは「$a=bq+r$ ; $0 \leqq r <b$という形に置ける」という事、
もう一つは、「この形式は一意である」という事である。
従って、
「$bq$ を数$b$ の倍数であって$a$ をこえない最大のものに
等しく取る $\Rightarrow$ どんな整数$a$ も、正の整数$b$ によって、
一意的な仕方で次の形に表される : $a=bq+r$ ; $0\leqq r <b$」
とは、もう少し砕いて記述すると、
「$bq$ を数$b$ の倍数であって$a$ をこえない最大のものに
等しく取る $\Rightarrow$ $a=bq+r$ ; $0 \leqq r <b$ が得られる、
そして、その形式は一意である」
となる。
ゆえに、これを証明するためには、
「$bq$ を数$b$ の倍数であって$a$ をこえない最大のものに
等しく取る $\Rightarrow$ $a=bq+r$ ; $0 \leqq r< b$ 」
と
「$a=bq+r$ ; $0 \leqq r < b$ という形式は一意である」
の2つを証明すれば良い。
この時、一意性の証明というのは、結論である
「$a=bq+r$ ; $0 \leqq r < b$ という形式は一意である」
という部分を証明するものであるから、厳密な意味においての
「$p \Rightarrow q$」という形式ではない。
ただし、これは結論を否定して矛盾を導く事で証明とする、
背理法という証明手法により証明する事ができる。
この、結論を否定する方法での証明手法である背理法のみ、
結論だけあれば成立させられる証明手法であるから、その事は
心に留めておくと良い。
証明手法とは、直接法、対偶法、背理法の3つのみである。
では、証明してみよう。
|
$bq$ を数$b$ の倍数であって、$a$ を超えない最大のものに等しく取る $\Rightarrow a=bq+r$ ; $0\leqq r<b$ となる. |
∵
$bq$ を数$b$ の倍数であり、$a$ を超えない最大のものと等しく取る時
$bq \leqq a$
∴ $0 \leqq a-bq$ __①
この時 $r=a-bq$ __② とおけば
$r+bq=a$
∴ $a=r+bq$
∴ $a=bq+r$ __③
また、$a-bq$ は$b$ より小さいか$b$ 以上のどちらかである。
従って、$a-bq$ を$b$ 以上と仮定する。
この時 $b\leqq a-bq$ より
$b+bq\leqq a$
$b(1+q)\leqq a$
$b(q+1)\leqq a$ __④
この時、当然ながら $q<q+1$ である事より
両辺に$b$ を掛けて $bq<b(q+1)$ __⑤
この時 ④ ,⑤より
$bq<b(q+1)\leqq a$
この時$bq$ は$a$ を超えない最大の数ではない。
∴ $bq$の最大性に反する。
∴ 矛盾。
∴ $a-bq$ は$b$ より小さい。
∴ $a-bq <b$ __⑥ とおけ
① ,⑥より
$0\leqq a-bq<b$ __⑦
また、⑦に②を代入する事より
$0\leqq r<b$ __⑧
従って、③ ,⑧より
$a=bq+r$ ; $0\leqq r<b$
以上より、上記の命題が成立する。
これで主要部分の証明が終わる。
ちなみに、オレンジの線を引いた部分が
「排中律」を使っている箇所である。
また、証明を行う際、ざっとこの形式に書き直してみると
分かるのだけれど、上から下へコツコツと論を引き出すだけで
証明を成立させる事ができる。
つまり、証明の際、上の情報を加工して
下の情報を作り出しているのが分かると思う。
ただし、この形式で論を導くのであれば、
下の情報を加工して上の情報を作り出しても証明にはならない。
(もちろん、逆(下から上)を言う事ができる場合もある。しかし、
その議論は、ある証明を行おうとする際、その証明で行う議論とは
また別の議論になってしまう)
これが、証明を行う上で最も重要な事である。
私の持っている本では、基本的に、証明部分に関して
この調子で議論を行う事ができる。
では次に、「一意性の証明」も行ってみよう。
「一意性の証明」に関して、どう証明しても良いとは思う
のだけれど、背理法での証明をここでは採用する。
| $a=bq+r$ ; $0\leqq r<b$ という表示形式は一意である. |
∵
「$a=bq+r$ ; $0\leqq r<b$ __① という表示形式が一意でない」と仮定すると
$a=bq_1+r_1$ ; $0\leqq r_1<b$ __② とも置け、この時 $q\ne q_1$ または$r\ne r_1$ である。
この時 ① ,②より
$bq+r=bq_1+r_1$ であり
∴ $bq-bq_1=r-r_1$
∴ $b(q-q_1)=r-r_1$
この時、左辺は$b$ の倍数であるから
$r_1-r$ は$b$ の倍数である。
∴ $r_1-r=br’$ ($r’$ はある整数) __③
また、この時 ① より$0\leqq r$ である事から
$0-b\leqq r-b$
∴ $-b\leqq r-b$ __④
また、②より$r_1<b$ である事から
$-b< -r_1$
∴ $-b+r< -r_1+r$
∴ $r-b<r-r_1$ __⑤
∴ ④ ,⑤より
$-b\leqq r-b<r-r_1$
∴ $-b<r-r_1$ __⑥
同様に ①より$r<b$ である事から
$r-r_1<b-r_1$ __⑦
また、 ②より$0\leqq r_1$ である事から
$-r_1\leqq 0$
∴ $-r_1+b\leqq 0+b$
∴ $b-r_1\leqq b$ __⑧
∴ ⑦ ,⑧より
$r-r_1<b-r_1\leqq b$
∴ $r-r_1<b$ __⑨
この時 ⑥ ,⑨より
$-b<r-r_1<b$ __⑩
また、③より
$r_1-r=br’$ である事から⑩に代入して
$-b<br'<b$
∴ $-1<r'<1$
この時、$r’$ は整数である事から
$r’=0$
また、③より
$r_1-r=br’$ である事から
$r_1-r=b・0$
∴ $r_1-r=0$
∴ $r_1=r$ __⑪
この時 ① ,②より
$bq+r=bq_1+r_1$ であり
⑪より$r_1=r$ である事から
$bq+r=bq_1+r$
∴ $bq=bq_1$
∴ $q=q_1$ __⑫
⑪ ,⑫が言える事より
この事は$q\ne q_1$ または$r\ne r_1$ であるという条件に反する。
∴ 矛盾。
従って、$a=bq+r$ ; $0\leqq b<r$ という表示形式は一意である。
以上より、上記の命題が成立する。
こんな感じで議論を展開する事ができる。
基本的に証明とは、このようなものなのだけれど、
慣れてしまえばなんてことはない、コツコツと上から下へ
議論を展開させているだけの事である。
ただ、私が証明に関して真に驚嘆するのは、
(コツコツと上から下へ議論を展開させているだけなのに!)
結論を得る過程が魔法のように感じる瞬間があるという事
であったりする。
そこまでの証明は、この場所では伝える事ができないのだけれど、
「証明とは、とても面白そうだ」と思ってもらえたなら、私自身とても
嬉しく感じる。