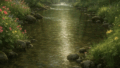「何が等しいか」により、数学記号が変化する事は
数学を行なっていて極めて興味深い事のように感じる。
具体的に、同値関係というものは、
「$A \Leftrightarrow B$」で表されるものだけれど、
$A$ と $B$ の間の等しさを表す記号の一つである。
$A$ と $B$ のどの面が等しいか、
それが変わると、等しさを表す記号も
自ずと変化する。
例えば、「 $ \equiv$ 」という記号がある。
「 $A= B$ 」とは、$A$ と $B$ の「値」が等しい時に
使われる記号だけれど、この「 $=$ 」の下にもう一つ線を引いたもの、
「 $ \equiv $ 」とは、両端の「余りが等しい」時に使う記号である。
「余り」とは、
ある数を「割る」事で初めて生まれる数であるから、
「 $ \equiv $ 」を使う時には、「何の数である数を割っているのか」、
それを、あらかじめ明記しておく必要がある。
この、ある数を「割る数」、それを明記する際、
その前につける記号を「 $mod$ 」と書き、「モッド」と呼ぶ。
従って、「$ A\equiv B$ ($mod$ $m$)」と書けば、
「$A$ を $m$ で割った余り」と「$B$ を $m$ で割った余り」が
等しい事を意味する。
この時、「余り」が等しい事にどんな意味があるのか?
この「 $ \equiv $ 」は、ガウスが導入した記号だそうで、
この記号を導入した事で冗長な演算処理が、大幅に簡略化
され、故に、高度な数式を、誰もが簡単に扱えるように
なったという。
このような事は、様々な数学記号の成り立ちにも言え、
良い具合に数学記号が作れたり、使えたりする事は、その後の
数学の発展に大きく関わってくる事でもあるという。
総じて、この世に数多ある数学記号の効用とは、
そのような部分にあるらしい。
また、色々な意味合いにおいて、等しさを取り出す、
それは数学を行なっていると、多くの場面で出くわす基本事項だろう
と思う。
故に、どのような記号で、どのような側面の等しさを測っているのか、
それが分かるようになると、とても数学が面白くなると思う。
数学記号の持つ奥深さや豊かさ、その意味を、
高校時代に全てではなくとも、もう少し理解出来たら良かったなと、
今日はそんな事を思いつつ、こんな文章を書いている。