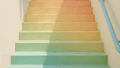私自身、数学の様々な定理を証明していると、
「定理の中には、前提条件のついたものがある」
という事に気づく。
この「前提条件のついた定理」というのは、
前提条件を証明の中で使う必要がある定理である。
そして、この「前提条件のついた定理」というのは、
その前提条件がなければ、定理が機能しない定理でもある。
従って、「前提条件つきの定理」を証明する際、その前提条件を
使わないと、定理そのものが証明できない場面というものが出てくる。
どこかの時点でその前提条件を使うのだけれど、
どこで使うかは、証明を行なってみないと分からない。
この時、この前提条件とは、どのようなものと言えるだろうか?
もし仮に、証明というものを
「ある材料(P)から、ある完成品(Q)を作る工程」と
見なしてしまえば、「その材料の一部」に前提条件は含まれる。
つまり、前提条件とは、結論を得るための
「材料の一部」であると見做せるように思う。
また、数学書を読み込んでいて「前提条件」が
何処にどの様に書かれているのか、それを探すのは、
証明の「仮定」を探す事と同じで比較的難しい。
故に、ある定理の前提条件を探し出せたら、
定理の仮定や結論と分離させて、何処までが前提条件なのかを
はっきりさせておくと良い。
前の記事で、私がノートに証明を書き写す際、「仮定(P)を最上段におく」と
記したのだけれど、「前提条件がついている定理であれば」、その前提条件を
最上段に書き写して証明に取り掛かっている。
つまり、「〇〇である時(前提条件)、PならばQ」と記して、
証明に取り掛かっている。
個人的な感想であるのだけれど、
前提条件のついた定理を証明できるようになると、
証明に対する理解の幅がとても広がるように
思う。
そして、証明に対する理解の幅が広がる、
それは数学において、とても大きな魅力の一つ
である。