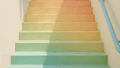今日紹介するのは、「数学の仮定」について。
私自身、高度な数学の理論書を読みこんでいると、
仮定が、常に「上段の位置」に書かれているとは限らない事
に気づく。
どこかには、書かれているのだけれど、
証明された命題や定理の下に書かれていたり、
命題や定理と分離されていなかったり、
サラッと何気なく書かれていたりする。
基本的に、証明というのは、
仮定と結論の「間」を埋める作業なのだけれど、
この仮定がどこに書かれているかを探す作業が、
数学書を読み込んでいて、結構、労を要する。
「仮定(論理の出発点)」を見つけさえしてしまえば、
そこから結論までコツコツと「論を導く」だけで良いのだけれど、
結論を導出するにあたって、どこが出発点か分からない状況が、
意外としんどい。
また、「仮定」というのは、結論がどの様な条件のもとで
成り立っているかを考え抜いた末に定めたものであると思う。
従って、どの様な状況を考えてその仮定を定めたのか、
それを意識すると、その仮定が存在している意味そのものが
よく理解出来るように思う。
私が、証明出来そうな定理を見つけたら、
『〇〇の時(ならば)、□□である』と、証明出来そうな定理の
フォーマットを固定させてしまう。
そして、それが何故成り立つかを考え抜く。
つまり、「〇〇の時(ならば)」と「□□である」の『間』を
考え抜く。
逆に、「□□なのは何故だろうか?」、それが数学書を読んでいて
疑問として生じれば、「こういう仮定が生じるからだろうか?」と考える事で、
「〇〇の時、□□であるのだろう」と推測でき、この間を埋められさえすれば、
自分自身の疑問に対して、証明が行える。
自分自身の疑問に自分自身で証明を与える作業も、意外と面白い。
数学の証明を行っていると、
「難しい」と感じる事も多いのだけれど、それは意外と
自分自身が知らなかったり、考えていなかったりする事が
含まれているからという事が多い。
上に記した事は、ちょっとしたコツなのだけれど、
数学上の技術として参考になれば、とても嬉しい。