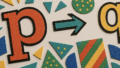私は、息抜きにゲームを行なう事がある。
その中で、『テトリス』や『ぷよぷよ』などのゲームは、
「数学に似ているなぁ」とよく思う。
どこがどう似ているか?
基本的に、私は約4000年分の古典代数学の定理一覧の証明に
しか触れていないので、「おそらく」としか言えないのだけれど、
「数学の流れというのは、論理の上から下への運動性」の
事だろうと思う。
何を言いたいかというと、数学の証明において、
仮定と結論を結ぶためには、(仮定を最も上段、結論を最も下段に
設定してさえしまえば)コツコツと上から下へ議論を
展開させるだけで良い。
また、『テトリス』や『ぷよぷよ』といったゲームは、
上から流れてくる「ブロック」や「ぷよ」をどう消したら
高得点に結びつくかを考えつつ、慎重に下段に
その「ブロック」や「ぷよ」を配置しなければならない。
沢山の「ブロック」や「ぷよ」を上手く組み上げて、一気に消してしまえば、
高得点が狙えるのだけれど、それが上手くいかないので試行錯誤したり、
組み上げ方を考えたりする。
この試行錯誤が、『テトリス』や『ぷよぷよ』の醍醐味だろうと
思うのだけれど、その事(この試行錯誤)が、とても数学の証明に
似ているように感じる。
数学の証明を行うためには、論理的に思考する事が
必要とされるのだけれど、論理というものを、
この『テトリス』や『ぷよぷよ』の「ブロック」や「ぷよ」に
相当するものとみなしてしまえば、「論理の欠片(ブロック)」を
証明の過程に上手く配置する事で、思いもかけない結論へと
議論を展開する事も出来る。
この時、証明の内部にどう「論理の欠片(ブロック)」を配置するかは、
その人のアイデアや発想によっているようにも見える。
数学において、その「アイデアや発想が極めて重要」である事は、
私が古典を学んできて得た感想でもある。
「どのようなアイデアで、どのような定理を作るか?」
そこに古代の数学者たちの矜持を感じるのだけれど、その事に想いを
馳せながら数学を学ぶと、より数学が楽しめるのではないか?
私は、そんなふうに考えている。